映画『俺ではない炎上』の公開にあわせて登場した体験型キャンペーンサイト「絶対にバズるSNS『Y』」が、SNS上で大きな話題を呼んでいます。
この「Y」は、ユーザーが投稿を行うとAIが“炎上シナリオ”を自動生成し、まるで本当に炎上しているかのようなコメントや拡散が再現される仕組み。
映画のテーマである「SNS社会における自己責任」「炎上の構造」「情報の暴走」を、ユーザー自身が体験するマーケティング設計が秀逸です。
映画を見ていなくても参加できる手軽さと、体験後に「作品を観たくなる」心理設計が完璧に噛み合った、“2025年型プロモーション”として注目を集めています。
本記事では、このSNS「Y」の仕掛けを、体験型マーケティングの観点から徹底分析します。
映画『俺ではない炎上』とは?
SNSでの「炎上」と「自己同一性」をテーマにした社会派ドラマ。
主人公が「自分ではない誰か」によって炎上の渦中に巻き込まれていく姿を通して、現代のネット社会の脆さと恐ろしさを描いています。
「誰もが炎上の当事者になり得る」というメッセージが、SNS時代に生きる私たちに強烈に刺さります。
炎上体験サイト「SNS Y」とは?
炎上体験サイト「SNS Y」とは、映画『俺ではない炎上』と連動した体験型プロモーション。
ユーザーが架空のSNSに投稿すると、AIが反応を生成し、共感から批判、そして“炎上”へと発展する過程をリアルに再現します。
実際に炎上の渦中にいるような心理を体験でき、SNS時代の怖さと拡散の仕組みを学べる、疑似炎上シミュレーションサイトです。
「絶対にバズるSNS」という名の皮肉
Yは、一見すると「インフルエンサーになれる」夢のSNS。
しかし投稿を重ねるごとにAIが「炎上」へと導き、コメント欄が荒れていく構造です。
つまり“バズる=炎上”という皮肉な真実を、ユーザーが体験的に学ぶ仕組みです。
AIが作る「疑似炎上体験」
ユーザーの投稿内容・写真・選択肢に基づき、AIが自動的にコメントや反応を生成。
「共感」「称賛」→「違和感」「批判」→「拡散」「炎上」という流れが段階的に再現されます。
体験中はまるで本物のSNSを使っている感覚で、心理的な没入感が非常に高いのが特徴。
「体験型マーケティング」としての完成度
「SNS Y」は、映画『俺ではない炎上』のテーマである“拡散と誤解”を見事に体験化した、体験型マーケティングの好例です。
単なる宣伝にとどまらず、ユーザーが自ら炎上を体感することで、映画のメッセージを感情として理解させる仕組みを構築。
体験と感情のリンクによって、作品の世界観が深く記憶に残るよう設計された、没入型プロモーションの完成形といえます。
視聴前でも興味を引きつける導線設計
Yは映画未視聴でも体験可能。
まず「炎上」を疑似的に体験させ、SNS上で「やってみた」「マジで怖い」と口コミを拡散させる設計になっています。
体験者が自然と映画の世界観を共有・宣伝する、UGC(ユーザー生成コンテンツ)型マーケティングの好例です。
H3:映画本編とリンクする“裏の意味”
映画を観たあとにもう一度「Y」を体験すると、
「自分の選択肢が映画の登場人物の行動と重なる」ような仕掛けに気づく構造。
体験と物語が双方向でつながる設計が、他のプロモーションと一線を画しています。
SNS「Y」から見える“現代炎上構造”のリアル
SNS「Y」で体験できる“炎上”の流れは、まさに現代SNS社会の縮図です。
小さな誤解や言葉の切り取りが、瞬く間に拡散し、無関係な人々までが攻撃や擁護に加わる。
誰もが「正義」を語る中で、本来の意図はかき消され、現実の人間関係や評判が崩れていく。
この構造は、私たちが日々SNS上で目にする炎上のリアルを、可視化し体感できる社会実験のようでもあります。
誰もが「加害者にも被害者にもなる」
Yでは「投稿者」としての視点だけでなく、「コメントする側」の反応も表示されます。
炎上の背景には、悪意だけでなく「正義感」「共感」「誤解」など複雑な感情が絡むことを体験的に理解できます。
バズること=正義ではない
SNS上では“いいね数”や“拡散力”が評価軸になりがち。
しかし「Y」では、注目されることがいかに簡単に“炎上”へ変化するかを体感できます。
つまり、マーケティングの本質である「注目を集めること」と「信頼を守ること」のバランスを問いかける設計になっています。
「俺ではない炎上」プロモーションが成功した理由
映画『俺ではない炎上』のプロモーションが成功した理由は、SNS時代の「共感」と「恐怖」をリアルに再現した体験設計にあります。
疑似SNS「Y」で誰もが炎上を体験できる仕掛けにより、ユーザーは映画のテーマを“自分ごと”として感じることができた。
SNS上で話題が自然拡散し、口コミが新たな波を生むことで、広告ではなく体験そのものが宣伝になる循環を生み出したのです。
ユーザーが「参加者」であり「語り手」になる
単なる広告ではなく、“体験を拡散したくなる仕掛け”が功を奏しました。
「怖かったけど面白い」「映画も気になった」といったリアルな感想が自然にX(旧Twitter)やTikTokで広がり、広告費をかけずに拡散力を獲得。
体験が“社会的議論”に昇華する設計
体験後のSNSでは、「炎上は誰のせい?」「匿名の責任とは?」といった議論が自然発生。
プロモーションを超えて、映画のテーマそのものが社会問題として議論される段階にまで発展しました。
まとめ|体験型マーケティングが映画を動かす時代へ
『俺ではない炎上』と「SNS Y」の仕掛けは、単なる宣伝ではなく、
「観客が物語の一部になる体験設計」を体現した事例といえます。
炎上体験という刺激的なテーマを、AI技術とSNS構造を掛け合わせて“安全に疑似体験させる”。
その結果、映画のメッセージがより深く心に残る構造になっています。
映画宣伝が“広告から体験へ”と進化した今、
「SNS Y」はまさに2025年のマーケティングを象徴する成功モデルといえるでしょう。
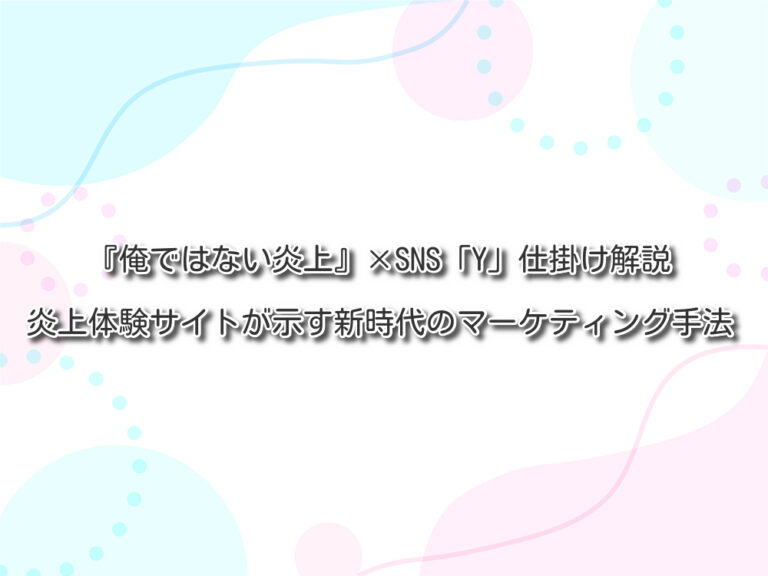


コメント